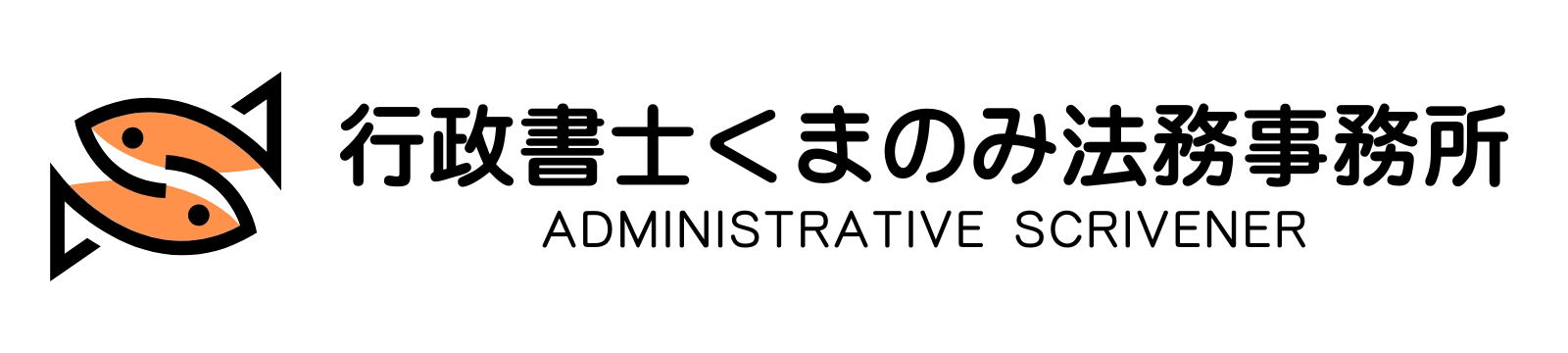中小企業の人手不足解消における外国人労働者雇用について

外国人労働者雇用の歴史
〜技能実習制度と育成就労制度のこれから〜
はじめに
日本の中小企業では、深刻な人手不足が続いています。少子高齢化が進み、国内労働力の確保が困難となる中で、「外国人雇用」の重要性はますます高まっています。
本記事では、中小企業の人事・採用担当者様に向けて、外国人労働者を受け入れる意義や現状、技能実習制度や育成就労制度の特徴、今後の法改正の見通しなどについて、分かりやすくご説明します。
外国人雇用に不安や疑問を感じている企業様にとって、制度の正しい理解と対応策を知ることが、円滑な受け入れの第一歩です。
外国人雇用の背景
人手不足が加速する日本社会
日本では生産年齢人口(15〜64歳)が年々減少し、多くの業種で慢性的な人手不足が課題となっています。特に、建設業、製造業、介護業、農業、宿泊業といった「現場を支える業種」においては、求人を出しても応募が集まらない状況が続いています。
中小企業では、大企業のように人材確保のためのリソースを割くことが難しく、経営そのものに支障が出るケースもあります。
外国人労働者という選択肢
こうした状況の中で、注目されているのが「外国人労働者」の活用です。外国人雇用は、単なる労働力の補填だけでなく、職場の多様性や国際的な視野を広げるという効果も期待できます。
特にアジア諸国から来日する若者たちは、日本の技術や働き方を学びながら、企業の現場で即戦力として活躍しています。
現在の外国人雇用制度の概要
技能実習制度とは?
「技能実習制度」は、1993年に創設された制度で、開発途上国の若者に日本の技能を学んでもらい、自国の経済発展に貢献してもらうという「国際協力」の趣旨に基づいています。
受け入れ企業は、実習生に対して実務を通じた技能教育を行う必要があり、制度上は「労働者」ではなく「実習生」という位置づけです。しかし、実態としては人手不足対策として活用される場面が多くなっていました。
技能実習制度の構造と期間
技能実習制度は、以下の3段階で構成されています:
- 技能実習1号(1年目):基本的な技能の習得
- 技能実習2号(2~3年目):習得した技能の実務応用
- 技能実習3号(4~5年目):さらに高度な技能の習得(条件あり)
受け入れ可能職種は約80職種と限られており、制度の運用は監理団体(組合など)と入管当局の監督下にあります。
特定技能制度の創設
2019年には「特定技能制度」が新設されました。この制度は、外国人が試験や実務経験により一定の技能・日本語能力を持っていることを前提に、「労働者」として就労することを可能にしています。
この制度は「人手不足対応型」の制度であり、特定技能1号と2号が存在します。特定技能2号は在留期間の上限がなく、家族帯同も可能なため、長期的な人材定着が期待されています。
現在の制度における課題
技能実習制度の問題点
技能実習制度は、制度の趣旨と実態の乖離が大きな問題となっています。具体的には以下のような課題があります。
- 実習という名目での過酷な労働
- 日本語や文化への不適応
- 労働者としての権利保護の不十分さ
- 監理団体による不正や不適切な対応
これらはメディアでもたびたび取り上げられ、制度の信頼性にも疑問が持たれています。
特定技能制度の課題
特定技能制度は、新しい制度として期待されていますが、以下のような課題が存在します。
- 日本語能力や技能試験のハードルが高い
- 情報提供やマッチング体制の整備不足
- 受入企業側の準備不足(支援体制、住居確保、教育など)
また、在留資格の更新手続きや、制度自体の理解不足も現場での混乱を招いています。
今後の制度改正の方向性
技能実習制度の廃止と「育成就労制度」の創設へ
政府は2023年11月、「技能実習制度を廃止し、代わりに『育成就労制度』を創設する方針」を打ち出しました。これは、技能実習制度の問題点を根本的に見直し、より実態に即した労働制度に改めるというものです。
育成就労制度の概要(予定)
「育成就労制度」は、外国人が日本企業で段階的にスキルを習得し、最終的に特定技能制度への移行を前提とした設計になる予定です。
主な特徴は以下の通りです:
- 目的の明確化:人材育成と労働力確保の両立
- 職種の見直し:特定技能制度に準拠
- 転籍の柔軟化:一定の条件のもとでの事業者変更を容認
- 支援体制の強化:企業に対し、日本語教育や生活支援の義務付け
- 労働者としての権利保護:労働基準法等の厳格な適用
この制度により、外国人労働者がより公平に、安心して働ける環境が整備されることが期待されます。
中小企業への影響と対応
中小企業が外国人雇用を進めるにあたっては、次の点が重要になります。
- 制度変更に即応できる体制の整備
- 外国人に対する労務管理や教育体制の確立
- 在留資格の確認と更新対応
- 地域社会との共生に向けた取り組み(住環境や生活支援など)
外国人雇用は単なる「採用」ではなく、「共に働き、育てる」姿勢が求められます。
まとめ
外国人雇用は中小企業の未来を支える力
人手不足に悩む中小企業にとって、外国人労働者の受け入れは有効な選択肢のひとつです。これまで活用されてきた「技能実習制度」には課題が多く、今後は「育成就労制度」や「特定技能制度」が主軸となっていく見通しです。
制度の理解と準備がカギ
法改正や制度の変化に柔軟に対応するためには、信頼できる行政書士や専門家との連携が欠かせません。人事担当者の皆さまには、最新の情報にアンテナを張り、制度を「知る」ことから始めていただきたいと思います。
外国人雇用のご相談は、行政書士くまのみ法務事務所までお気軽にどうぞ。
在留資格の申請、就労制度の導入支援、日本語研修制度の構築など、トータルでサポートいたします。