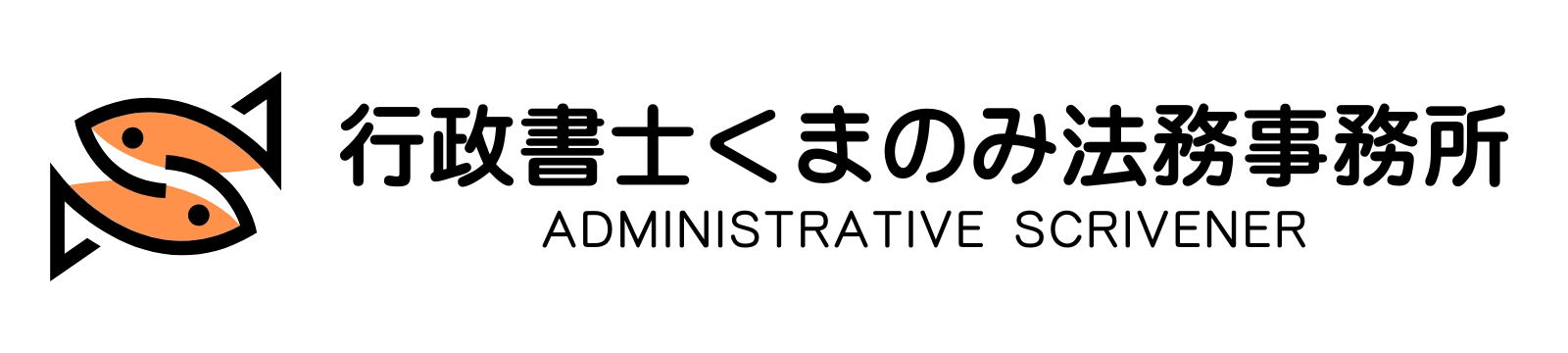『消防設備士A社が挑戦した建設業許可申請の成功物語』
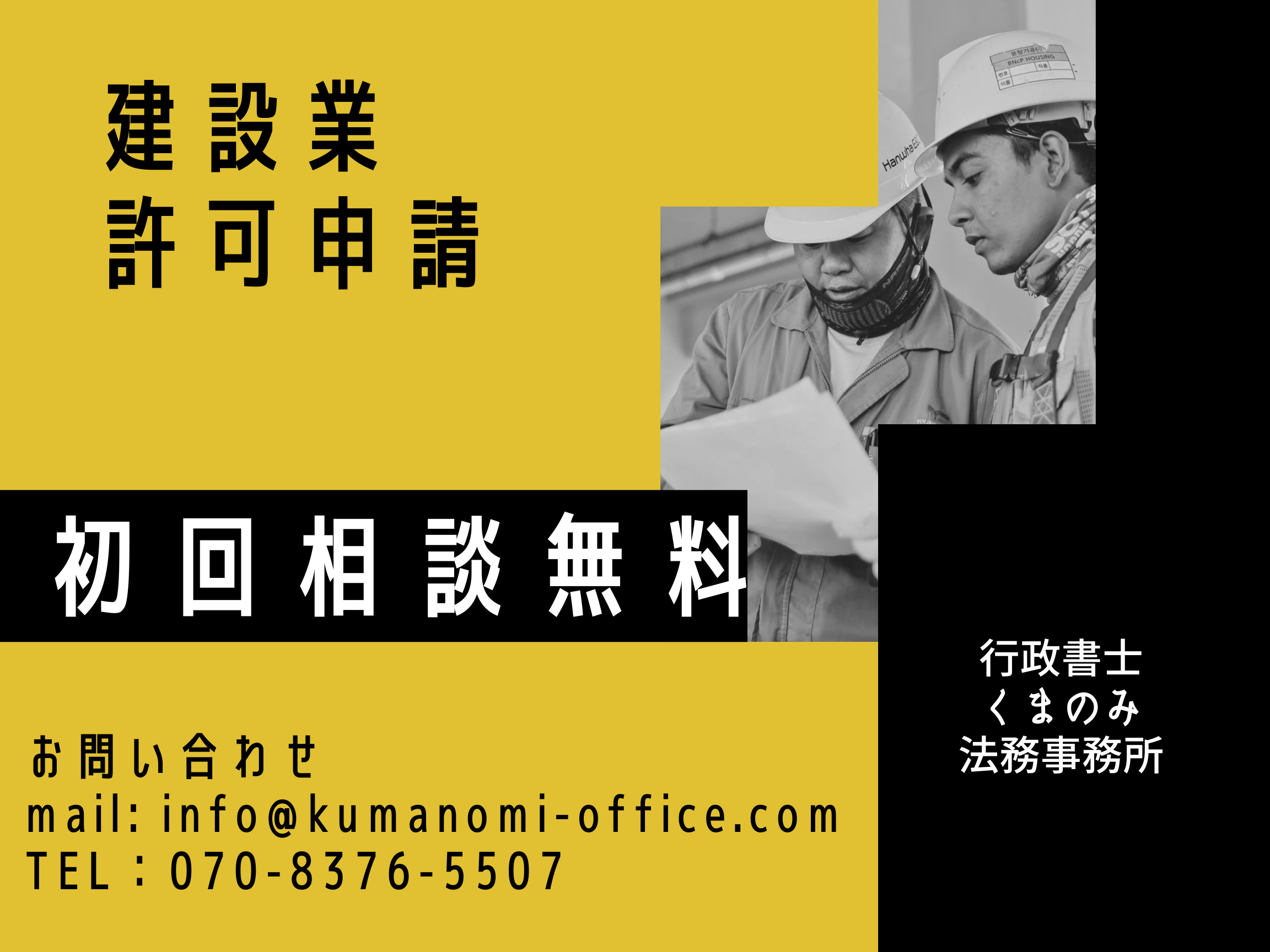
イントロダクション
消防設備を設置するA社にとって、建設業許可の取得は業務拡大のために必要不可欠でした。しかし、初めての申請には多くの課題が伴い、代表者Bさんはどこから手をつけるべきか悩んでいました。この記事では、A社がどのようにして許可申請に成功したか、その過程を紹介します。
1. 許可の種類を決定する
Bさんは、まず自社がどの建設業許可を取得すべきかを決定するところから始めました。消防設備工事を主に行うA社の場合、工事規模などから一般建設業許可が最適であると判断し、その申請に取り組むことにしました。
- 営業所の所在地と許可の種類
A社は広島県内のみで営業しているため、知事許可を申請することになりました。もし複数の都道府県にまたがって営業する場合は、大臣許可が必要です。
2. 必要な要件を確認
次に、Bさんは建設業許可の要件を確認しました。
- 経営経験のある役員
Bさん自身が過去に10年以上の経営経験を持っていたため、この要件は問題ありませんでした。 - 専任技術者の要件
消防設備の工事に関する資格と実務経験が求められました。A社には資格を持つ技術者がいたため、要件を満たしていました。 - 財産的基盤の確認
許可取得には500万円以上の資本が必要であり、A社は自己資本でこれを証明することができました。
Bさんは「要件を全て満たしているか確認することで、自信を持って申請に臨めました」と振り返っています。
3. 書類の作成と準備
建設業許可申請には多くの書類が必要です。A社は以下のような書類を準備しました。
- 申請書一式の作成
A社は、申請書に加え、技術者の資格証明書、過去の工事実績書、定款などを整えました。これらの書類をミスなく揃えるために、Bさんは専門家の協力を求めました。 - 証明書の取得
役員に関する身分証明書や履歴事項全部証明書など、法務局や市区町村から証明書を取得しました。
「行政書士のサポートがあったことで、申請書類の不備がなく、スムーズに進められました」とBさんは述べています。
4. 許可行政庁への申請と審査
A社は、準備した書類をもとに、広島県の建設業許可窓口に申請しました。申請の際には、以下のポイントに注意しました。
- 申請先と申請方法の確認
窓口での直接提出と郵送が可能でしたが、Bさんは行政書士に同行してもらい、直接提出することで、即座に確認を受けました。 - 手数料の支払い
新規許可申請の際には、収入印紙を使って手数料(9万円)を支払いました。
申請から審査完了まで、知事許可の場合はおよそ1ヶ月かかりましたが、無事に建設業許可通知書を受け取ることができました。
5. 許可取得後の展望
A社は、無事に建設業許可を取得し、消防設備工事に加えて、さらに大規模なリフォーム工事にも取り組むことが可能になりました。Bさんは「初めての許可申請で不安が多かったが、行政書士のサポートを受けたおかげでスムーズに進められた」と述べ、今後の展望に自信を持っています。
まとめ
建設業許可申請には、多くの書類や厳格な要件を満たす必要があります。しかし、専門家のサポートを受けることで、これらのハードルをクリアし、スムーズに許可を取得することができます。くまのみ法務事務所では、建設業許可申請に特化したサービスを提供し、安心して手続きを進められるようサポートします。許可申請でお困りの方は、ぜひご相談ください。